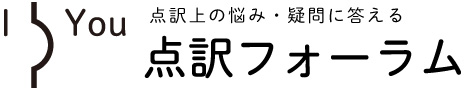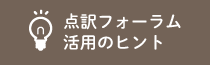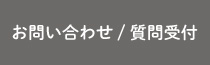手書きの時代、そして点字図書館という職場の思い出
2025年7月1日
パソコンが普及していなかった時代、点訳とは点筆で一点一点刻むか、点字タイプライターを用いるかの方式でした。それこそ熱意と忍耐力によってコツコツと作成される点訳書は、それぞれが世界に1冊しかない貴重な存在だったわけです。
私自身は10代の終わりから日本点字図書館の通信教育で点字を学び、やがてそこは私の職場になって、貸出・出版書製版・点訳者養成・点訳書校正などの業務を経験しました。
就職が80年代初めでしたので、パソコン点訳の黎明期前夜に当たる頃だったでしょうか。
出版書製作においても、点字データと連動する自動製版機の導入以前は、足踏み製版機によって製版していました。指は6点キーを叩きながら、ペダルを踏み込んでマスを進めていく方式で、2枚重ねの亜鉛板に点字を刻印していきます。
点訳といっても、町工場のような音や金属臭にあふれた仕事場での肉体労働といった趣がありました。
ひときわ哀愁を帯びた、コンカンカン…は、誤った点を、金槌型の修正器で叩いて潰す音。手書きの点字の修正では、丁寧に点を消して裏から薄めた糊を引く作業が必要でしたが、出版の現場では点の修正も、槌打つ響きの伴うダイナミックなものだったわけです。
修正器は、ばねによって金槌がリズミカルに上下するようになっているので、意外に軽やかではあるものの、多くの点を潰すことはけっこう大変ですし、修正が何行にも及ぶ場合は全体を製版し直すことも。いうまでもなく紙に比べてコストがかかるものなので、やってしまった感も大きいのでした。私の場合、マスあけを直されることによって点字表記を「ひたすら叩いて身に付けた」という実感があります。
亜鉛板を二つに折って2枚重ねにするのは、間に紙を挟み、ローラーが高速で回転する印刷機を通して点字を印刷する仕組みだからです。
1冊の出版書の亜鉛版数十枚はずっしりと重く、木の箱に収めて地下書庫に並べていました。持ち上げ損なって足の上にでも落としたら、大変なことになるでしょう。
印刷機の回転ローラーや裁断機の刃など、ちょっとした不注意で怪我につながるものたちに囲まれた町工場的環境は、自動製版機導入後も変わらぬ点字出版所の情景だと思います。
けれども次第に自治体や企業で点字が必要とされる場面が急増し、外注・急ぎの仕事が立て込むようになって、点訳書の入力のような落ち着いた仕事がメインだった時代は遠くなりました。
その後点訳書製作の部署に移った頃は、パソコン点訳が飛躍的に広まりゆく時代で、新たな点訳者養成講習会が行われるようになりましたが、図書館草創期や手書きの時代から長く点訳を続けて下さっている方々も多くご健在でした。
図書館創立者であった本間一夫(職員も外の人も、敬愛を込めて本間先生と呼んでいました。私も退職して10年以上経ちますので、いまは外の者として、以下、この懐かしい呼び方を使わせていただくことにします)は、点訳書1冊1冊を点訳者名とともに記憶していました。
何よりもご自分自身本が読みたいという願いから発足させた施設だっただけに、点訳・朗読ボランティアへの想いは深かったと思います。
点訳による蔵書製作が根付くうえで、点訳奉仕活動を提唱した社会教育家・後藤静香氏の尽力も忘れることはできません。
戦争時3千冊あった点字本は、疎開先で大切に守られました。
この苦難の時代にも、防空壕の中で蝋燭の光をたよりに点訳を続けられたかたがあったことや、点訳すると20数冊におよぶドストエフスキー『カラマーゾフの兄弟』の点訳を病床でコツコツと取り組み、仕上げられた点訳者さんのエピソードなども折に触れ語られたものです。
そんな記憶を留めたいとの思いから、奥付だけでなく標題紙にも点訳者名を記し、古い時代の点訳書冒頭には、点訳に対する感謝の言葉を述べたページが挿入され、部分的に傷んだページを転写によって補修しながら、長く読み継がれてきました。
手書きの時代の特徴として、点字表記の統一というようなこともまだ徹底されていなかったこともあり、各点訳者の個性も含めて、点訳作品と捉えていたように思います。
パソコン点訳と違って修正は大変労力を要することから、その本の中で一貫した表記であれば尊重せざるを得ない事情もあったのでしょう。
しかしそれだけに点訳の質が低下しないよう、養成課程は大変厳しいもので、初期には指導部と称していた担当係では、添削によってお伝えしたことを理解していただけない場合には、どんなにご熱意があっても練習継続をお断りしていました。
点訳は決して点訳者の生きがいだけを目的とすべきではなく、それを必要とする人に正しい点訳書を提供するために行うべきもの。先輩職員から教えられたこの考え方は、点訳する人が心すべき指針を含んでいるように思います。
熱心に志して下さる方に対して、基準に達しないことを理由にお断りすることには反論もあると思いますし、点訳の裾野を広げる活動においては、もっと寛容な姿勢が求められるでしょう。
けれど昔も今も、長く活躍していらっしゃる方は、点訳に対する使命感とご自身への厳しさをお持ちであることが共通するように感じます。それが結局は生きがいとも重なることは自然の成り行きなのでしょう。
図書館を支えて下さった点訳者のお一人お一人を思い起こすと、いかなる時期も点訳とともにあり、一日も欠かさずコツコツと積み重ねて下さったご努力の尊さを感じます。
紙に手書きする点字について、思い出すことがあります。
パソコンの時代になっても、講習会と通信指導の課程を終えての卒業本は手書きで点訳していただくことになっており、それが仕上がったときには、本間先生ご自身点筆をとって感謝状を差し上げていました。
しかし先生は多くの言葉を書きたいとの熱意が高じて節約のため、助詞や助動詞を次行に送る行移しを多用するので、点訳する際には望ましい処理ではないことを、係の職員が言い添えてお渡しすることもありました。
手書きでは単に行末のマス数を把握しそびれて、書いているうちに助詞まで入らなくなるケースも多かったのですが、先生は、多分今はない特別製の、点のサイズが小さくて書けるマス数の多い点字器を愛用していたくらいに「たくさん書きたい人」でしたので、おそらく行末の空白がもったいなかったのだと思います。
職場の70周年記念誌を編纂したときに収集したエピソードとして、戦中・戦後には紙の調達にもずいぶん苦労があったようで、樺太から紙を積んできた船が撃沈され、2年間も海底に眠っていた塩水を含んだ紙さえ、貴重なものとして点訳に使われたといった話も印象に残りました。
用紙の節約のためというわけではないのですが、点訳書でも出版書でも手書きの頃は、脱字やマスあけの修正がその行で解決できない場合、やむなく助詞・助動詞を次行に送ったりして、ページ内でずれが解消できるように処理していたことを思い出します。
出版書では「ぶら下げ」と称していた裏技がありました。
両面書きではページ行を除いて1ページ17行ですが、裏のページは17行目の下に18行目を入れることが可能でした。紙の下部ギリギリまで点があると傷みやすいので、決して望ましいことではないのですが、どうしても何文字か入らない!という場合の奥の手だったのです。
このほかデータによって複部数作成することができなかった手書きの時代には、サーモフォーム複写の方式でコピーすることもよく行われていました。
触図は現在なら作図ソフトを使ってグラフィックデータを作成することができますが、ルレットで点線を描いたり、手触りの異なる布や紙を両面テープで貼り付けたり、糸を貼ったりして作成したものを、サームフォーム複写する方式が一般的でした。
図ではなくても、学習参考書など必要なものは、紙の点字をサーモフォーム原版にして、複部数製作していたのです。
あんな不便さ、こんな大変さもパソコンによって一気に解消され、「手書きの時代」は昔のことになりました。
ですが方式の転換につれ変化していくこともあれば、変わらず受け継がれていくこともあるはずです。
ブライユの考案から200年のメモリアルイヤーを点字と共に生きている私たち。今の時代を「あの頃」と振り返ることになったとき、点字はどのようなものになり、点訳作業はどのように変化していることでしょうか。 (K)