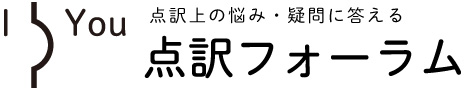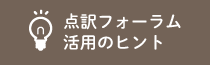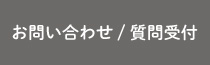今年もよろしくお願いいたします
2025年1月1日
皆さま、あけましておめでとうございます。
2025年もどうぞよろしくお願いいたします。
今年は、点字が考案されて200年の年になります。
日本点字委員会発行の『ルイ・ブライユの生涯 天才の手法』と『資料に見る点字表記法の変遷 慶応から平成まで』を参考に、点字の考案と日本における点字の翻案の経緯について改めて紐解いてみたいと思います。
1809年1月4日に、フランスのクーヴレ村に生まれたルイ・ブライユが、縦3点、横2点の6点点字のシステムを作り上げたのが、1825年でした。10歳でパリ王立盲学校に入学し、シャルル・バルビエが盲学校に持ち込んだ12点点字に出会ってから4年、ルイ・ブライユ16歳の年でした。
バルビエの12点点字は、フランスの王立科学アカデミーに「普通の読み書きは目に訴えるものだが、バルビエ氏は触覚に訴える先進的な読み書きの方法を考案した」と報告されていました。盲学校の生徒たちは、それまで、1冊4.5kgもある浮き出し文字で学んでいたことにくらべ、この新しい読み書きに夢中になったのですが、「綴りと文法が存在しないこの方法では、ある程度読み書きはできるようになったが、目の見える人と同じようには」いきませんでした。しかし、聡明なブライユ少年は、これに改良を加えて、さらに使いやすい読み書きの方法に取り組みました。1821年から1824年までの3年間、「ブライユは、日中は授業に追われていたが、じゃまが入らない早朝や眠れない夜に、独自の体系の実験をしていた。作業道具は寮に持ち帰り、紙、点筆、点字盤などに囲まれて寝てい」て、夏休みなどの長い休暇には、クーヴレで、点字の考案に没頭したそうです。15歳になる頃には、バルビエの一マス12点を指の下にぴったりと収まる6点に縮めていて、1825年には点字の基本的な形をほぼ完成させました。そして、ブライユが考案した点字記号の利点は生徒や教師に即座に理解されました。
その後、1829年には、ブライユの点字記号解説書が発行され、点字楽譜の基礎もできていました。1832年に数符を考案、1834年に音楽記号が完成、1836年に「w」のアルファベットが加えられました。そして、1837年ブライユの点字を使用した最初の完全な点字書が発行されます。
ですが、フランスで点字が正式の文字として認められるまでは紆余曲折があったようです。理由の一つには、晴眼者との壁を無くすために、盲人も晴眼者と同じ読み書き方式を使うべきだという考えが根強かったこともありました。
フランス政府がブライユの点字体系を盲人が読み書きする公式な方法として正式に認めたのは、ブライユの死後2年たった1854年でした。
日本に点字が初めて紹介されたのは、1866年(慶応2年)幕府の外国奉行に随行した岡田攝蔵(せつぞう)による『航西小記』でした。「盲人に教ゆるに・・・文字を以てせず、紙の面に凸(たか)く小点を印し、例えばイの字を印すれば●の印をなし、●●をロとなすが如く・・・」と書き、フランスでは、点字で盲学校の教育が行われていることを紹介しています。
その後、1879年(明治12年)には、目賀田種太郎によってアメリカの教育事情が紹介されます。目賀田は、ブライユの点字を詳しく説明した上で、「ブライユの点字を日本に採用する場合、必ずしも欧米の用い方に従う必要はなく、日本語は日本語として限定した使い方があってもよい」と、日本語の特徴を活かした点字が翻案される必要を発言しています。日本の点字が制定される10年以上前のことです。
点字が日本の盲学校教育に使用されるのは、1886年(明治19年)楽善会訓盲院に赴任した小西信八が「漢字仮名交じり文のまま凸字本として視覚障害児に与えられている教育を見て、いかに労多くして効少ないかを痛感した。何とかして視覚障がい者自身で簡単に自由に読み書きできる文字がないものかと熱望し」たことに始まります。
1887年(明治20年)、小西は上野の東京教育博物館に館長・手島精一を訪問し、欧米先進国の視覚障害者はどんな文字を使用しているかを尋ねました。手島はルイ・ブライユの考案した6点点字こそ世界唯一の視覚障害者用文字であることを力説します。小西は手島からイギリス製の点字盤と点字に関する本を借り、試みに小林新吉(新潟県出身)に点字のローマ字綴り方を教えました。小西の指導を受けた小林は、1週間で自由に書けるようになり、本人の喜びはもとより、他の生徒への影響も大きいものでした。このことが小西に日本語点字翻案への意向を固めさせました。小西は教諭の石川倉次に日本語の仮名文字を表現する工夫を勧め、石川がその研究に着手しました。
その後、ご存じのように、東京盲唖学校で、教員・石川倉次案、教員・遠山邦太郎案、生徒の伊藤文吉・室井孫四郎案が提出された点字選定会が開かれ、4回の会議を経て、石川倉次の案が日本の点字として選定されました。1890年(明治23年)11月1日でした。今年は日本の点字誕生から135年になります。
石川倉次が、1937年(昭和12年)に吹き込んだレコードがあります。そのなかで石川は、「私は日本の盲人の心に目を与えるという考えで、ブ氏(ブレイル氏)の六点をメにしました・・・ この点字が今後わが国幾百万の盲人のあかりとなって、目あき以上の功績をわが文化の上に立てられる人の出て来られる事を心から祈って止みません。」と話しています。
このようにして、現在の6点点字は、フランスのルイ・ブライユによって考案され、多くの人々を経て日本語に翻案され、引き継がれてきました。この点字の文化を、私たちはさらに次の世代に確実に届けていきたいものです。
私たち、点訳に携わるものの大切な役目として、視覚障害者の文字である点字を読み書きする仲間を増やしていくことがあると考えています。
すなわち、中途で目が不自由になり、点字を必要としながら点字を読めない人の点字習得をサポートすること
そして、小・中学生や一般の市民の方に点字を広め、日常生活で見る点字に気づき、その点字をみんなが読めるようにすること
さらに、点訳者を養成して、共に活動する仲間を増やすこと
点訳に携わる私たちは、日々の点訳活動に取り組むだけでなく、この3点も常に心に留めて、点字文化を引き継ぐ活動も進めていきたいと思います。
今年も協力して点字を読み書きする仲間を増やす努力をしていきましょう。 (M)
【資料】
1.『ルイ・ブライユの生涯 天才の手法』2012年6月1日初版発行 C・マイケル・メラー著 発行 日本点字委員会
2.『資料に見る点字表記法の変遷 慶応から平成まで』2007年11月1日初版発行 編集・発行 日本点字委員会