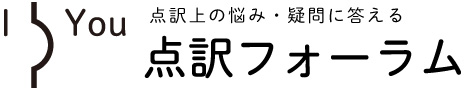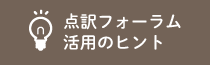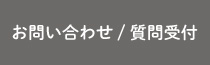触地図の役割について
2025年5月1日
まず、触地図の例を二つご紹介します。
2022年2月24日、世界中を震撼させる出来事が起きました。そうです、ロシアによるウクライナ侵攻です。テレビの報道番組では、しばらくの間、毎日のようにトップニュースで取り上げていたほか、特集のテーマとして、専門家をゲストに戦況やその後の展開などについて分析や議論が、今でも行われています。言葉による説明が基本ですが、特にこの種の報道では、それを補うため、しばしば地図などの画像を用いることがあります。「ロシアの支配エリアは、ドネツク州のこの辺りまで拡大していますね…」などと。地図など視覚に訴えることで、報道内容が理解できたり、わかりやすく伝えることにもつながっていると思います。それだけ、地図には言葉以上の説得力があるといえます。
しかし、残念なことに、私には直接地図を見ることができません。言葉だけでもかなりの部分は理解できますが、触地図があればもっと深く知ることができるのに…。触地図に触れながらニュースを聞きたい、そんな思いが徐々に強まってくるようになりました。「百聞は一見に如かず」ならぬ「百聞は一触に如かず」でしょうか。そのような中、知人からN大学のW先生が、立体コピーでウクライナの触地図の作製と提供をしている、との情報を知り、早速申し込みをしました。今、手元にウクライナ、ウクライナとその周辺諸国の2枚の地図があります。前者には、キーウ・ハルキウ・ルハンシク・オデーサなどの主な都市が示されています。ロシアが併合したとされる、東部ルハンスク・ドネツクなどの州の区分までは示されていませんが、都市の位置がわかるだけでも、大いにニュースの助けとなっています。ハルキウでの戦闘と聞けば「ああ、ロシア国境沿いでの戦いだなあ」ということが簡単にイメージできるようになります。後者の地図は、ウクライナと周辺国との位置関係を示したもので、ポーランド・ハンガリー・バルト三国…、などウクライナとの位置関係がイメージでき、触地図がなかった頃と比べると報道内容の更なる理解に結びついていると感じています。これは大きな違いです。
もう一つは、昨年1月1日に発生した能登半島地震では、最も被害の大きかった輪島市・珠洲市などの地名を頻繁に耳にするようになりました。しかし、輪島・珠洲と聞いても半島のどの位置にあるかが、ニュースを聞いただけでは、すぐにはなかなかイメージできません。そこで助けとなったのが、ここでも触地図でした。具体的には『新版 日本地図 改訂 第4版』(東京点字出版所)に、それぞれの市が載っていました。これにより、半島内での位置だけでなく、金沢市との位置関係もわかるようになりました。贅沢を言えば、いたるところで道路が寸断された国道249号などの道路地図があると、さらに能登半島を知ることにつながったかもしれません。
以上はいずれもマスコミ報道において、触地図が言葉や文字を補完する役割として有効ではないかと考えている例です。
次に、「道路地図」「地域地図」「構内図」といった、いわゆる生活に直結する身近な触地図について取り上げます。これらは移動する上で大きな助けとなる地図です。事前に移動経路や移動先などの情報を知ることにより、安全かつスムーズな移動につながることが期待できます。
「道路地図」は主に歩行訓練などの際によく利用していました。指導教諭が、予め訓練コースの触地図を作製し、事前学習を通じてイメージづくりをさせ、訓練に入る方法をとっていました。事前に学習したイメージと現実との間には当然違いはありましたが、安心感を得られたのは大きかったと思っています。手元には、そのときに使用したサーモフォームの「道路地図」がいっぱいあります。
「地域地図」は、居住地周辺の地図のことで、道路はもちろんのこと、ほかに主な建物や交差点などの情報も含まれた、利用者が個別に必要とする地図です。このため、個別に依頼し作製してもらう必要があります。「地域地図」によって、居住地周辺を単独で移動できる可能性が高くなります。生活に最も欠かせない触地図といえるかもしれません。
「構内図」は駅や公共の建物内などの案内図です。建物内の各種設備全体の配置や目的地までの経路を予め把握できるので、スムーズな移動につながります。
地図情報は、今はスマホでも簡単に調べられるようになりましたが、視覚障害者にとっては、それはあくまでも言葉による情報でしかありません。これに対して、触地図は、実際手で触れることで、頭の中で地図情報をイメージできる点が大きな違いといえます。
N大学のW先生によれば、「道路地図」や「地域地図」のニーズは高いと聞いています。また、ニーズに対応できる体制づくりが今後の課題と言っておられました。特に「地域地図」は、正に個々の利用者に合わせた地図です。必要なときに必要な触地図が手に入る、そんな世の中になって欲しいものです。
私は、触地図を含む触図を読むのが元々大好きで、中学生の頃には、社会科・地理の地図帳を、暇さえあれば読み漁っていたことを覚えています。ヨーロッパから中東、東南アジア、南アメリカ…と。そこでは国の広さ、周辺国との位置関係、首都の位置などを調べるのが楽しみでした。触地図に興味を持つようになったのは、小学生のとき、教室の壁に張られていた、北海道から九州までの立体の地形図を見たのがきっかけです。立体図ですから、高低差がわかります。富士山の高さが際立っていたこと、河川の長さの違い、平野と山地の違い…など、休み時間にはよく触っていたのを思い出します。そうした背景もあって、冒頭で示したような報道番組では、触地図の必要性を強く感じるようになりました。
今回は触地図の役割などを中心に取り上げましたが、どんなに必要とされていても、わかりにくかったり、読みにくい地図では意味がありません。作製にあたっては、わかりやすく・読みやすくするための工夫や触読の特性などにも配慮した地図を目指していただければと思います。
また、私が触地図を強く推奨しているかのような印象を持たれた方もいるかもしれませんが、決してそういうつもりはありません。視覚障害者の触知能力には、失明時期の違いを含め、極めて個人差が大きいといわれています。したがって、言葉による説明が理解しやすい方には言葉で、触地図の方が理解できる方には地図を、というように柔軟な対応が重要と考えています。くれぐれも、触地図万能主義にだけは陥らないでいただきたい、これが私の本意です。 (I)