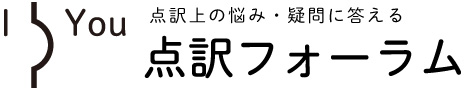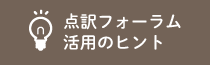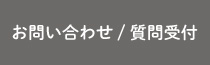第5章 書き方の形式(3)
その3 詩歌・戯曲などの書き方
1.p160 1.詩 (2)
初めて詩の点訳をしています。「てびき」の(1)(2)の説明と例2、例3の関係がよく分かりません。行や連による書き出し位置の変化や、1行が点字で2行以上になる場合の処理について、例2と例3の違いを教えてください。例2と例3のどちらの書き方にするのかを決めるのに何か決まりがあるのでしょうか?また、詩が2行では書ききれず3行になる場合はどのように処理するのでしょうか?
【A】
詩の例について
例1 書き出し位置に差がない、常に3マス目から書き出す詩です。この場合、詩の1行が点字で1行に入らない場合は、次行は行頭一マス目から書きます。一般の文の書き方と同じです。
例2 書き出し位置に差がある詩の書き方です。この例では、書き出し位置が下がっているときに、点字では4マス下げて、7マス目から書いています。そして、それと区別するために、1行が点字で1行に入らない場合は二マス下げる書き方をしています。3マス目から書く行が1行に入らない場合は、次行5マス目から書き、7マス目から書く行が1行に入らない場合は、さらに二マス下げて9マス目から書いています。
例3 書き出し位置に差がある詩ですが、例2と異なり、1行が点字で1行に入らない場合は二マス上げる書き方をしています。書き出し位置が下がっているときには点字では4マス下げて、7マス目から書くのは、例2と同じです。この書き方の場合は、3マス目から書く行が1行に入らなければ、次行行頭一マス目から、7マス目から書く行が1行に入らなければ、次行は5マス目から書きます。
詩の1行が点字で2行にも入らず3行以上になる場合は、2行目と同じ位置から書き始めます。2行目が9マス目から書き始めていれば、3行目も9マス目から書きます。2行目が5マス目から書き始めていれば、3行目も5マス目から書き始めます。
書き出し位置に差がある詩を点訳する場合は、「てびき」では、例2または例3で書くことをお勧めしています。このどちらの書き方でも構いません。
例2と例3でどちらがお勧めと言うことはありませんが、詩の1行が点字で3行になるよりは2行に入った方が読みやすいので、詩の1行が長い場合は、例3のほうがよいと思います。
2.p160 1.詩 (2)
『宮沢賢治の視点と心象』という本を点訳しています。その中で、心象スケッチ「春と修羅」の詩の全文が載っています。その解説文に「宮沢賢治はここの部分を、一行ごとにほぼ一字づつずらして、ジグザグに書いている。」とあります。
確かにこの詩は行頭を行ごとにずらして書いている部分がありますが、点訳をする際にもずらして書かなければならないのでしょうか。行頭が開いていると、触読の際に疑問に感じるのではと思い、迷っています。
【A】
「春と修羅」は、一部書き出し位置が、5~7行に渡って1文字ずつ下がり、また5~7行にわたって、1文字ずつ上がって行くような書き方になっています。点字では1行のマス数も限られているので、原文どおりに書くことはできませんし、書いても読みにくいことになります。
そこで、その部分も書き出し位置は、行頭3マス目から書いて、点訳挿入符で断ることにするのがよいと思います。
解説文に「宮沢賢治はここの部分を、一行ごとにほぼ一字づつずらして、ジグザグに書いている。」と書いてあるとのことですので、ここで、点訳挿入符で《点訳では、すべての行を3マス目から書いています》のように断ればよいと思います。
3.p161 1.詩 (4)
小学生向けの詩集です。詩の冒頭に題名と作者名が同じ行に書かれています。例えば、題名が「木」で、作者名が「与田準一」の場合でも、作者名は次行の末に書くのでしょうか。空白の部分が多く、児童向けでもあり、作者名を見落とすのではとも思います。二マスあけなどで同じ行に、題名と作者名を続けて書くなどはできるでしょうか。
【A】
詩の場合は、タイトルの次の行の行末に作者名を書くのが一般的ですので、そのように統一するのがよいと思います。
詩のタイトルと作者名の書き方は、その本の中では統一して書きます。
詩のタイトルと作者名を二マスあけて同じ行に書くことはできますが、すべての詩がタイトルと作者名が1行に入るかどうかわかりませんので、一般的な書き方のほうがよいと思います。次行に作者名が来ることが分かっていれば、読み落とす心配も少ないと思います。
4.p160 1.詩 (4)
詩や短歌、あとがきなど行末近くに名前を入れる場合は奇数マス目から入れるのでしょうか
【A】
行頭を偶数マスあけして書くのは、見出しにも使用される11マス目程度までで、行頭から半分以上あいている場合は、偶数マスあけに拘らなくてよいとされています。
5.p160 1.詩
詩のレイアウトについて質問します。
例: 本文(行頭から) 四つの車輪
(次行頭から)が徐々に平行する時
原本通り、次行に改行して、この「が」を書いて良いでしょうか? 四つの車輪がを、続け書くべきでしょうか。
次のようなところもあります。
・・・もろも
ろの思念たちは
祈った
りとんぼがえりを・・
【A】
詩でしたら、原文の通り
■■ヨッツノ■シャリン
■■ガ■ジョジョニ~
となります。
地の文であれば、一続きに書き表す語はマスあけをして書く事はしませんが、「詩」の場合は、作者が意図を持って行を替えていて、それが作品になっているのだと思いますので、原文の通りに行替えをすることになると思います。
その詩人の別の詩集などに掲載されていないか、その場合も同様に行替えしてあるかなども比較してみてはいかがでしょうか。
6.p160 1.詩
詩の中に文中注記符を使用することはできますか。
例: 弧の下を
「弧」に注が付いている場合、説明はどうすればよいでしょうか。
【A】
文中注記符は、詩の中で用いることができます。
ご質問の場合は弧の直後に文中注記符を入れ、詩が終わったところで、1行あけまたは仕切りのための線を入れるなどして、説明を入れるのが分かりやすい方法になると思います。
7.p160 1.詩
児童向けの詩集です。※のついた語の下方に説明が書いてあります。
ひとつの詩の中で、ひとつのものもあれば、4個くらいのものもあります。
また、説明が短いもの、例えば、※おかん→お母さん。もあれば、かなり長いものもあります。短いものは、その語の後に書き、長いものは、詩の最後に書く方法か、短いものも,長いものも番号を振って、詩の最後に書くのか。
どのように処理したら良いでしょうか。
【A】
詩集は詩を作品として鑑賞するものですので、詩の中にカッコで囲んで説明を入れることは避けた方がよいと思います。
詩に文中注記符を付け、一つの詩がおわるたびに、仕切りのための線を入れて、文中注記符をつけた語の説明を入れるようにするのがよいと思います。
その詩に一つだけの場合は、数字を挟まない文中注記符になります。詩がかわるたびに、文中注記符に付ける数字も、1からになります。
8.p164 1.詩 例4
「てびき」例4にある「ふるさと」の書き方について質問です。歌詞の番号が二桁になった場合、歌詞部分が偶数マス目から始まることになります。この場合、数字の後ろを一マス空けて奇数マス目から始めるべきでしょうか。それとも、偶数マス目からそのまま書いても問題ないのでしょうか。
【A】
この書き方は、歌詞が5マス目から揃っていて読みやすいのが特徴で、多くは点字で1ページに収まるというメリットがあるので、よく用いられている方法です。
歌詞番号が二桁になるような場合に、例4の方法を採ると、1番~9番と10番以降は
歌詞の書き出し位置が変わることになりますので、違和感を伴います。
歌詞番号が二桁になる場合は、例5の「学生時代」のように番号だけを1行に書き、改行して歌詞を書くような方法がよいと思います。
9.p166 2.短歌・俳句・川柳など
漢詩・短歌のレイアウトについて教えてください。
1.挿入文で、七言絶句の漢詩が、二句の後で改行する形でレイアウトされています。漢詩は部分的な訓点文で、送り仮名は無く、返り点・句点だけが施されています。
題
一句。 二句。
三句。 四句。
書き下し文にして訳すにあたり、原本通り二句の後で行替えするべきか、行替えせずに三句目を続けてよいのか、または1句ごとに行替えすべきか、どうすればよいでしょうか。
2.詠み人違いの短歌が3つ挿入されています。下のようなレイアウトで、行あけはありません。
短歌1
詠み人1
短歌2
詠み人2
短歌3
詠み人3
本文とこれら挿入文の間は前後1行あけますが、短歌・詠み人のレイアウトはいずれが適当でしょうか。
①-1:短歌の後に2マス空けて詠み人を書き、改行して行空けはせず短歌2、3を書く
①-2:短歌の後に2マス空けて詠み人を書き、短歌間は行空けする
②-1:短歌の後、改行して行末に詠み人を書き、改行して行空けはせず短歌2、3を書く
②-2:短歌の後、改行して行末に詠み人を書き、短歌間は行空けする
【A】
1.書き下し文にすると1行に1句と2句は入らないと思います。
漢詩の形態を保って書くには
■■1句
■■2句
■■3句
■■4句
と1句ごとに行替えして書くのがよいと思います。1句が1行に入らない場合は次行行頭から書きます。
2.短歌の場合は、歌だけで1行に収まることはないので、二マスあけて作者を書くのは、あまり形が良くないと思います。
原文で次行行末に書いてあるのでしたら、短歌の次の行に行末に揃えて作者を書くのが一般的であると思います。
短歌3首が挿入された形になっているのでしたら②-1の書き方でよいと思います。
②-2の書き方もあると思いますが、行をあけなくても挿入された短歌であることがわかると思います。
10.p166 2.短歌・俳句・川柳など
文中に短歌や俳句を引用する場合、原文に行あけがなくても本文との間を行あけしたほうがよいのでしょうか? 書き出し位置は下げた方がよいのでしょうか?
【A】
句集や歌集では3マス目から書きますが、文中に引用されている場合は5マス目から書くことも多く、この場合も前後を行あけしたほうがよいと思います。3マス目から書き出す場合は、必ず前後の行あけが必要です。活字書では行あけがなくても短歌や俳句が挿入されていることが一見して分かりやすいのですが、点字では分かりにくいので、このような配慮が必要です。
11.p166 2.短歌・俳句・川柳など
短歌や俳句のマスあけについて、5・7・5・7・7 の区切り目はすべて一マスあけとなるのでしょうか。 文中に文の終わりと解釈できる箇所(倒置法での表現と思える場合などですが)があっても2マスあけることはないと理解すればいいのでしょうか。
詩の場合、1行中に文の終わりがある時 (句点はない)は2マスあけていたのですが、短歌や俳句も同様の扱いと理解していました。短歌や俳句と詩の扱いは違うということでしょうか。短歌・俳句・川柳・冠句は短詩形ゆえに文の終わりと解釈できても2マスあける必要性がないと考えるのでしょうか。 基本とする考え方をご教示ください。
【A】
詩・短歌・俳句の書き方を示している第5章その3では、書き始めの位置や行替えについて提示しているだけですので、マスあけについては、第3章、第5章の「その1」のルールに準じて書くことになります。
その意味では、短歌や俳句だから、二マスあけは絶対にないとは言い切れません。
しかし、現在は、点字で読点を使用しなかった時代とは異なり、提示された主題の後ろ、倒置法の区切り目、感動や呼びかけを表す独立語の後ろなどでは二マスあけをしていませんので、俳句や短歌のなかで二マスあけを考えることはほとんどないと思います。「てびき」の例のなかでも例1、例2、例4、例5、例6などは、主題の提示や倒置法などと考えると二マスあけかどうか悩んでしまいます。
加えて、短歌や俳句はとくに韻律が重視されますので、二マスあけを入れることで流れが止まる感じになることを避ける意味合いもあるように思います。
破調の句や歌で明らかに二つの文からできている場合などを除き、俳句や短歌では基本的に一マスあけと考えてよいのではないでしょうか。
12.p166 2.短歌・俳句・川柳など
サラリーマン川柳を点訳中です。
1.原本で1句を3行に書き分けてある場合、2行目または3行目がページをまたぐ場合の対応、雅号だけページをまたぐ場合の対応はどうしたらよいでしょうか。
句の頭から次のページに移った方がよいでしょうか。雅号は行末に揃えているのでページをまたぐとわかりにくいと思います。また、句が1行で書いてある場合も同じです。
1つずらすと、その他の句にも影響するので、最終的に、句の途中や句と雅号が離れている場合は、同じページに収まるように調整したほうがよいのでしょうか。
どのような点訳の仕方が読みやすい点訳なのか分からなくて悩んでいます。
2.川柳の中は、一マスあけで点訳していますが、「。」「!」「?」が句中にある場合は、二マスあけにしても良いのでしょうか。
【A】
1.句と句の間を1行あけて書く場合は、句の途中でページが変わっても、句と作者の間でページが変わっても構わないと思います。1行あいていれば新たな川柳であることが分かりますので、それ以外に行あけはしない方が分かりやすいと思います。ただ、句の変わり目が1行目の場合も1行あけます。
2.句点がある場合は後ろを二マスあけ、疑問符・感嘆符でも文末と判断できれば二マスあけになります。
たとえば、
話聞け!スマホいじるな!「メモですが」
投資しろ?俺の財布を透視しろ!
のような場合は、
話聞け!■■スマホいじるな!■■「メモですが」
投資しろ?■■俺の財布を透視しろ!
となります。
13.p166 2.短歌・俳句・川柳など
「てびき3版 Q&A」のQ137の回答に「(前略)あるひとつの歌がページの最後の行で終わった場合でも、次の歌は新しいページの1行目から書きます」と記載されています。
点訳フォーラムのQ&A「p166 2.短歌・俳句・川柳など」の回答には「句の変わり目が1行目の場合も1行あけます」と載っています。
「てびき Q&A」に従って処理してある点訳に対しての校正で迷っています。
【A】
「てびき3版Q&A」は、一人の歌人の歌集で、短歌だけが並んでいる場合ですので、一首終われば、次の歌に入ることがわかります。ですから、ページの変わり目でも次ページの1行目をあけなくてよいと思います。
点訳フォーラムのQ&Aはサラリーマン川柳で、作者と作品が書いてあったり、他の要素が入ってきたりしますので、歌だけが並んでいる歌集とは異なります。1句が終われば、次ページに移る場合もかならず1行あけた方が分かりやすくなります。
校正の場合は、点訳者がいずれかの方法を選択して点訳していて、読むのに差し支えがなければ、その方法に従って校正してよいと思います。
14.p166 2.短歌・俳句・川柳など
挿入文の和歌に番号がついているときの点訳について教えて下さい。
原本は、
・・・3種の歌を詠みました。
(1)おほ君の~
心はわくとも~
(歌の説明あり)
(2)ひんがしの~
はこやの~
(歌の説明あり)
(3)
という文です。
他にも和歌の挿入はたくさんありますが、ここのみ(1)(2)(3)と上に番号がふってあります。他の和歌は普通に3マス目から上の句、5マス目から下の句にしています。この挿入文を1行あけのあと
(3マス目から)(1)■おおきみの■~
(「おおきみの」の書き出し位置から二マス下げた位置から)こころわ■わくとも■~
のようにしてもよろしいでしょうか。
3首とも上の句、下の句ともに1行におさまりますが、上の句がぎりぎり32マス目まできます。もし2行にまたがる場合はてびきp164、165の歌詞の例のように番号を一マス目からにしたり、和歌の前の行に番号を持ってきてもよいでしょうか?
【A】
(1)(2)(3)の番号を5マス目から書いて、次行に3マス目から和歌を入れる方法と、番号を3マス目からかき、次行は5マス目から書く方法のいずれかがよいと思います。
■■■■(1)
■■オオキミノ
■■■■ココロワ■ワクトモ
■■(1)■オオキミノ
■■■■ココロワ■ワクトモ
タイトル中の見出しや、レイアウトによって判断してよいと思います。
15.p166 2.短歌・俳句・川柳など
挿入されている短歌の書き方を教えて下さい。
原本で1句を以下のように4行に書き分けています。
尋ねてもまた
たづねてもたづねても
多津禰つきせぬ
剣術のみち
「てびき」p166[処理1]に「3行書きの短歌も原文に準じて書くことを原則とする。」とあります。上の句を3マス目と5マス目から2行に書いた場合、下の句の書き出し位置は何マス目にすればいいのでしょうか。
【A】
原本で4行に書かれていることは原本通りに書いてよいと思いますが、始まり位置が異なっていても、すべて3マス目から書いた方が分かりやすいと思います。
視覚的な効果のために行頭の書き出し位置を変えたように思われます。
■■尋ねてもまた
■■たづねてもたづねても
■■多津禰つきせぬ
■■剣術のみち
16.p166 2.短歌・俳句・川柳など
俳句の詞書きについて、短い詞書きが多く5マス目書き出し1行で収まるものがほとんどですが、長く2行以上になるものもあります。
長い詞書きは7マス書き出し、1行で収まる場合は5マス書き出しと混在しても良いでしょうか。または全て7マス書き出しに統一が必要でしょうか。
【A】
詞書きについては、書き出し位置を下げたり、カッコで囲んだりして書くこと以外に特に決まりはありません。詞書きであることが分かればよいと思います。5マス目から書き、次行は二マス下げて書いてもよいと思いますので、詞書きはすべて5マス目から書き、次行は7マス目から書いてもよいと思います。
詞書きの書き出し位置が変わるより、すべて5マス目から書きだした方が読みやすいと思います。
または、すべて7マス目から書き出し、次行は二マス上げて書く方法ももちろんよいと思います。
17.p166 2.短歌・俳句・川柳など
次のような連句があります。
曼珠沙華ぬっと出てただ咲くばかり 桂子
鎌を交互にあげる蟷螂 鈴代
自転車で大きな月を追いかけて 陽一
道行く人のハミングを聞く 蒼子
むささびの親子が住むという樹洞 柚子
数千坪の苔の絨毯 悟
のように続いていきます。
このレイアウトはどのようにすればいいでしょうか。
作者名は行を替えて行末近くに書くことを原則とするとなっていますが、行を替えていいものかどうか。かといって、二マスあけにすると、最初の発句は1行に収まりません。
作者名の書き方、また短句を二マスさげるのか、など、レイアウトをどのようにするのがいいでしょうか。
【A】
すべて3マス目から書き始め、作者名は句の後二マスあけて書くのがよいのではないでしょうか。1行に入らない場合もあるかも知れませんが、分かりやすいと思いますし、短句を二マス下げなくても十分に分かると思います。下げることによって1行に入らなくなった場合、行頭のマスあけが複雑になりますので避けた方がよいと思います。
18.p169 3.戯曲・対談などの書き方
対談に使われているアルファベットについてお尋ねします。
A. ファウルズが・・・・。
O. 彼が・・・。
というように、対談者の名前がアルファベットで表されており、アルファベットの後にピリオドがあります。
このピリオドは省略してもよいでしょうか。それとも省略せずA.■■ファウルズが・・・。と書くべきでしょうか。
【A】
アルファベットの後のピリオドは、後ろ一マスあけとなりますので、このままでは、対談としては読みにくいものになります。
次のいずれかの方法をとるのがよいと思います。
1.発言者の後に、第1小見出し符か第2小見出し符を用いる。この場合、ピリオドを付けたままでも、ピリオドを省略してもどちらでも構いません。
2.ピリオドを省略して、A、Oのあと二マスあけて、第1カギで発言内容を囲む。
二マスあけただけで発言内容を書くのは、わかりにくいので、第1カギを用いた方がよいと思います。
原文のピリオドは、Aさん、Oさんを表すのに、便宜的に付けたとも、イニシャルを表しているとも解釈できますが、「てびき」p48 5.により、省略しても差し支えありません。
19.p169 3.戯曲・対談などの書き方
漫画の書き方について質問します。
1コマの中に人物Aさんがいます。其のコマの中にAさんを挟んで吹き出しが2個ありそれぞれにセリフが書かれています。
1 「あ」「お疲れ様です」
2 「絵は書けたけど」「文字は何を書こうかしら」
3 「なーんか」「久しぶりに赤毛のアンよみかえしたくなっちゃった」
4 「後悔したくない」「きもち?」
このように同一人物のせりふを第一かぎで括った場合のマス開けは2マス明けでよいですか。てびきやフォーラム等で調べた限りではそのように考えました。色々な人との話し合いでは一マスあけで良いのではとの考えもありました。
【A】
漫画のレイアウトは、文章で表現する場合と異なり、一コマの中での人物の大きさや配置などによって変わってくると思いますので、一コマの中の同一人物のセリフは、一つのカギに収めた方が分かりやすいと思います。
人物の後ろ二マスあけとして以下に書きます。
1
外大A■■「ア■オツカレサマデス」
2
外大A■■「エワ■カケタケド■モジワ■ナニヲ■カコーカシラ」
3
外大A■■「ナーンカ■ヒサシブリニ■~
4
外大A■■「コーカイ■シタク■ナイ■キモチ?」
のようになります。
20.p169 3.戯曲・対談などの書き方
「指導者ハンドブック第5章編」の戯曲・対談などの書き方でについてお尋ねします。
問2 源三(モノローグ)で、人物名の後二マスあけではなく、カッコの前はマスあけなしになるのは、どうしてでしょうか。
「表記法」p122リア王物語内の例で
コーディーリア第2小見出し符■(独白)
とあり、記号の原則でと言うことでしょうか。
「てびき」例1-2
真紀■■(収に)
など、二マスあけになる場合と混乱するのですが、ポイントを教えてください。
問3 インタビュアー(棒線)の後は一マスあけですが、これは二マスあけの例と考え、人物名のあと小見出し符使用にした時、インタビュアー(棒線)の後も書き方の規則どおりに小見出し符使用でも大丈夫でしょうか。
問4 情景の説明で
場所 荻窪の中華料理店
時間 午後1時頃
中華料理を囲みながら・・
行あけ
ですが、段落挿入符で囲まないのはなぜでしょうか。
文の最初だから囲まなくても分かるからなのか。また、囲んでもよいのか。
【A】
問2 この場面は、源三としのの対話の形をとっていますが、このセリフだけは「モノローグ」であることを示しているので、このカッコは、注釈的説明に当たります。ですから前の語に続けて書きます。
問3 インタビュアーを棒線で表した場合、棒線のあと小見出し符にすることはできません。小見出し符類は、言葉を含む記号類に付けることはありますが単独の記号に用いることは想定されていません。
原文で、インタビュアーを棒線で示してある場合は、問4の書き方となります。
問4 この問いは、戯曲ではなく対談です。p170【処理1】で対談での話し手の動作や表情等を記すカッコには第1カッコを用いることが書かれていますが、対談の設定の説明などは、戯曲とは異なっていますので、段落挿入符を用いるという規則はありません。
21.p169 3.戯曲・対談などの書き方
海外のドラマのシナリオを翻訳した本です。
情景説明が行頭から書かれており、前後は1行あけてあります。点訳上は3マス目から書き始め、文中の段落は行替えしましたが、それでも文章の前後は第1段落挿入符を用いた方が良いでしょうか。
情景の説明途中で1行あいている場合があります。段落挿入符で前後を囲んだ場合、文中に1行開けても差支えがないでしょうか。
【A】
段落単位の情景説明には第1段落挿入符を用いるのが原則ですので、原本で行頭から書かれていても、3マス目から第1段落挿入符を用いて書いた方がよいと思います。
第1段落挿入符のなかで行替えがあっても構いませんが、原文で1行あいていた場合、場面が変わったり、時間が経過したり、情景説明の視点が変わったりしているのかも知れませんので、一度段落挿入符を閉じて、1行あけて、改めて第1段落挿入符を書いてもよいと思います。
22.p169 3.戯曲・対談などの書き方
『不思議というには地味な話 新版 近藤聡乃エッセイ集』の最初と最後に漫画の部分があります。
点訳フォーラムの質問や指導者ハンドブックのコボちゃんの例などを参考に、戯曲に準じて書こうと思い、戯曲の書き方についても、点訳のてびきの他、点訳フォーラムや指導者ハンドブック、点字表記法などの資料を当たりました。
調べてみても、戯曲の書き方に従うのが難しい箇所が何点かあり、方法に迷っています。
漫画の形式
・四コマ漫画ではなく、1ページの中に大小複数のコマが縦横に配置されている形式です。
・四角で囲まれた中に主人公の語りがあり、各コマにはセリフと思っていることが違う形の吹き出しで書かれています。
・セリフは必ず1コマずつにあるわけではなく、2コマ~6コマにまたがる形で語りのみがある部分もあります。
質問
①セリフは第1カギで囲むとして、思っていることを第1カッコで囲むと、ト書きと混ざってしまいます。凡例か点訳挿入符で断って、思っていること又はト書きに第2カッコを使うことはできるでしょうか。
②主人公の語りは情景説明とは違うので、段落挿入符は適当ではないように思います。セリフの話者のように3マス目から「語り」と書き、小見出し符のあとに語り部分を書くのがいいのでしょうか。
③4コマ漫画のように1コマずつに動きやセリフがあるわけではなく、吹き出しが一切ないコマいくつかにまたがって主人公の語りがある部分があります。
その際は、コマの番号を3~6のようにまとめて書き、それぞれのコマに何が示されているかを記入すればよいのでしょうか。
【A】
試し読みはできませんでしたが、後ろの漫画の部分だけは見ることができました。
後ろの部分は、右ページに5コマあり、左ページは新しい見出し「3.おしまいになった話」とあり、やはり4コマあります。
ただ、ストーリーになっている訳ではありませんので、漫画の書き方にこだわらなくてもよいように思います。
そのところに点訳挿入符で《5コマの漫画》のように断わり、各コマに何が書いてあるかにこだわらずに
(夜、机に向かって)
「それからしばらく時間がたって、ぱらぱらと読み返してみると」
(場面が、楽しげに自転車に乗っている様子に切り替わる)
「アリャー、そういえばそんなこともあったなどと懐かしくなりました」
のようにしてはいかがでしょうか。
《4コマの漫画》
(スイカの販売所で、多くのスイカをポンポンとたたきながら)
「チョットした油断で『これは一生忘れられないだろう』というほど傷ついてしまいました。」
(「これだ」とスイカを選び、ぶらさげて、よろよろと「重い」)
「忘れたい」
のように考えて見ましたが、もっと工夫ができるかもしれません。
漫画の書き方に規則や実例が示されていませんでしたので、その目安として「指導者ハンドブック」に1例を掲載した経緯があります。ただ、漫画とひとくくりにされる作品の中にも、多種多様な描き方がありますので、ハンドブックの書き方に当てはめられない場合は、この例やコマ割りにこだわらずに、工夫して点訳してもよいと思います。作品によっては吹き出しのセリフのみをカギで囲むものと限定せず、この場合も、上記の案のように著者が語っている言葉をカギに囲んで書く方法もよいと思います。ただ、適宜点訳挿入符で断ることは必要です。
23.p172 4.手紙文や公用文の書き方
遺稿集などに出てくる手紙文についてです。
①手紙本文の最後に、行替えし行末に寄せて書かれている「敬具」「敬白」などの結びの語
②手紙本文の後に、行頭から少し下げて書かれている日付
③更に行替えし、行末に寄せられた差出人の名前
④日付と同じ行に書かれた差出人の名前が1行で収まらない場合
⑤最終行、日付よりさらに書き出し位置を下げて書かれている宛名
これらの書き出し位置は、それぞれ何マス目からになりますか。
【A】
点訳ですので、原則として原文と同じ位置に点訳するようにします。
① 「敬具」「敬白」「草々」などは原文通りに行末近くに書きます。
行末にぴったり揃えて書かなければならないというものではありませんので,前の行との関係で、23マス目とか、25マス目程度で構いません。
② 日付は、5マス目あるいは7マス目から書くとよいと思います。
③ 行替えして行末近くに書きます。
④ 日付と同じ行に差出人を書く場合は、日付のあと二マスあけて書きます。
この場合、日付を5マス目から書けば1行に収まるのか、7マス目から書けば収まるかを検討します。そして日付と差出人名が1行に収まらない場合は、日付の下の行の行末近くに差出人名を書きます。その場合、上の行より少なくとも二マスは下がった位置から書き始め、1行に収まらない場合は、続きを差出人名の1行目から二マス下げて書きます。
⑤ 宛名は、行のはじめの方に書きます。一般には、相手の名前が一番上に書かれると思いますので、3マス目から書くのがよいと思います。日付より下がって書いてあっても7マス目より下に書くことは避けた方がよいのではないでしょうか。
原文通りの位置に書く場合でも日付を5マス目から書いたら、同じ5マス目か、下がっても7マス目からは書き始めたいと思います。
この辺は、規則性の強いところではありませんので、上記を目安にしていただければと思います。
24.p172 4.手紙や公用文の書き方
組織名、役職、氏名が続く場合の件です。「出版に寄せて――◯◯◯◯」という見出しのあと行を変えて、所属の組織名と肩書、氏名が続いて中点もなく1行で書かれています。原本は、氏名の前は一マスあいていて、氏名は書体を変えてあります。この場合どのように書いたらよいでしょうか。3つが違う要素なので、その間は二マスあけでいいでしょうか?組織名のあと、うしろ7マス位あきますが、意図的に行替えして、肩書と氏名を書く事はしないほうがいいのでしょうか?
【A】
このような場合は、組織名・肩書き・氏名を行末に揃えて書きます。行末に揃える場合は少なくとも行頭は、10マス以上あけることになります。
所属・組織名、肩書きなどを行末に揃えて書く例は、「てびき」にはあまりありませんが、p173の公文書の差出人のような書き方になります。
行末に揃えて書きますので、1行に収まることはほとんどありませんが、1行に収まる場合は、組織名、肩書きなどと氏名の間は二マスあけます。
1行に収まらない場合は、できるだけ組織名、肩書きなどの区切りで行を替えますが、行末の収まりなどのバランスも考えながら行替えをすることになります。
2行以上になる場合は、2行目以降は、1行目より二マス下げた位置から書き始めます。
例えば
行頭12マスあけ トーキョート■チジ■■コイケ■ユリコ
行頭12マスあけ フクオカケン■キョーイク■イインカイ
行頭14マスあけ キョーイクチョー■■サトー■イチロー
行頭10マスあけ フクオカシ■ホケン■フクシキョク
行頭12マスあけ セイカツ■フクシブ■ホケン■ネンキンカ
行頭12マスあけ カチョー■■ヤマダ■イチロー
のようになります。
25.p172 4.手紙文や公用文の書き方
「てびき第3版指導者ハンドブック」第5章編p31にある「公用文の書き方」です。
「中山市福祉会館利用登録団体各位」の点訳の仕方を回答例で確認しました。
■■ナカヤマシ■フクシ■カイカン■リヨー■トーロク改行
■■■■ダンタイ■カクイ
このように2行に書かれていますが、2行目をこのように書く理由が分かりません。
【A】
手紙や公用文で、一つの宛名や差出人が2行以上にわたる場合は、見出しの書き方に準じて、1行目より二マス下げて2行目以降を書きます。
公用文などの場合は、宛先の次に差出人を行末近くに揃えて書きますので、相手に対する敬意を表す意味でも、相手をできるだけ行の前の方の位置に収めることが必要になります。
相手が複数の場合は、各相手の書き出しを揃えて、数行に分けて書きます。
また施設名と役職名(~センター 所長~様)を書くときなどは、役職名から次行に移し、行頭を上の行と揃える場合もあります。
26.p172 4.手紙文や公用文の書き方
エッセイ集の最後にある日付の書き方については、「Q&A第2集」Q122では行頭から少し下げて書いてある日付は5マス目から書くのが一般的と書かれています。このエッセイは日付が行末に書かれているのですが、その場合も5マス目からでよいでしょうか。それとも原本通り行末に書いた方がよいのでしょうか。
【A】
特に決まりはありませんが、年月日は長くなることもありますので5マス目から書くと落ち着くと思います。
ただ、「6月吉日 筆者」のように、行末に署名と共に書いてあったりする場合は、行末に揃えて、収まりよく書いたり、行末に日付と署名を2行に分けて書いたりすることもあります。かならず原文通りというわけではなく、点字での読みやすさや収まりも考慮して決めるのがよいと思います。
27.p172 4.手紙文や公用文の書き方
文章の中に手紙文が挿入されています。
原文
ストラテンバーグ市教育長、カーメン・ストゥープ博士
拝啓
わたくしは・・・送る所存です。
敬具
一市民より
宛先と拝啓を行頭1文字目から、「わたくしは」が行頭2文字目から書き始めています。
敬具、一市民よりは右端に書かれています。
点訳する時は、宛先(2行になります)と拝啓は1マス目からでよいでしょうか。
文末を右詰にすると、敬具が27マス目、一市民が25マス目からの書き出しで良いでしょうか。
手紙文では拝啓のあと1文字あけて本文を始めますがそれに合わせてなくてもよいでしょうか。
【A】
相手の職名、名前などは一マス目から書く書き方もありますが、「てびき」ではp173に3マス目からの例を示しています。
「ストラテンバーグ市教育長、カーメン・ストゥープ博士」は役職と敬称付きの名前になりますので、読点を省略して
■■ストラテンバーグ市教育長
■■■■カーメン・ストゥープ博士
と書くのが、一般的な書き方になります。
次行、3マス目から「拝啓」で改行
次行、3マス目から 「わたくしは~」と本文を書き、「敬具」と「一市民より」はお考えのとおり、行末に書いてよいと思います。
28.p172 4.手紙文や公用文の書き方
手紙の差出人の書き方について、「あなたの最も忠実、誠実で従順なしもべ、***より」というように、名前の前に長い修飾語がついている場合、書き出し位置と2行になったときの2行目の書き出し位置はどのようにすればいいでしょうか。 例えば、3マス目から書き出して1行で終われば、3マス目からでも構いませんか。
【A】
手紙の差出人は行末近くに書きます。墨字の手紙でも差出人の名前を行頭近くから書くことはないと思います。点字の手紙でも同じです。
行頭10マス以上(できれば12マス以上)あけて、書き始め、複数行になる場合は、1行目より二マス下がった位置から書き始めるのが一般的です。
1行に入っても、3マス目から書くと言うことはありません。
29.p172 4.手紙や公用文の書き方
高校野球の申請書のレイアウトについて伺います。
一人一人の情報の後、次のような文言があります。行末のカッコ内の数字は質問のため付けたものです。この質問欄では、所在地、校名、校医等の記載は、原本ではいずれも1行に収まっています。
選手は参加資格規定に相違ないことを証明します。
昭和58年5月27日(1)
所在地 沖縄県北中城村字屋宜原415番地(2)
校名 沖縄県立北城ろう学校(3)
校長 當銘正幸(4)
選手健康証明書(5)
右の者、いずれも健康診断の時点で異常のなかったことを証明します。(6)
昭和58年5月27日(7)
校医 井手泰之(8)
校正をしていますが、点訳者は(1)(5)(7)を5マス目から、(2)(3)(4)(6)を3マス目から、(8)を19マス目から書いています。また(4)の後は行あけしていますが、(2)の後は行あけしていません。そのような書き方でよいのでしょうか。
(3)(4)(8)は行末に書いた方が良いのではないかと思いますが、その場合11マス目以降でよいのでしょうか。また書き出しは奇数マス目の方が良いですか。(4)と(8)の書き出し位置は行末に書くにしてもマス目を変えた方がよいのでしょうか。(1)と(7)の日付は原本では書き出し位置が違いますが、どうすればよいでしょうか。
(1)から(8)までの書き出し位置を教えていただけないでしょうか。
(2)と(4)の後は原本通り行あけしたほうが良いでしょうか。
【A】
校長と校医、それぞれの証明書を一つに納めたものですので、(4)と(5)の間は1行あけるのが適切だと思います。
1行目は3マス目から
(1)5マス目から
(2)(3)(4) 13マス目から
(5)5マス目から
(6)3マス目から
(7)5マス目から
(8)13マス目から
上のように書けば無理なく入るようです。
所在地は3行になります。2行目3行目は1行目から二マス下げた位置から書きます。(2)と(3)の間は行あけしない方がよいと思います。
行末に揃える場合は、同じ書類の中ですので、(8)も(2)(3)(4)と揃えた方がよいと思います。書き出し位置が異なっても間違いと言うことはありませんが、揃えた方がすっきりします。日付も5マス目からと揃えた方がよいと思います。書き出し位置が異なるから間違いと言うことはありませんが、書き出し位置がバラバラになるより、揃えた方がきれいな点字になると思います。